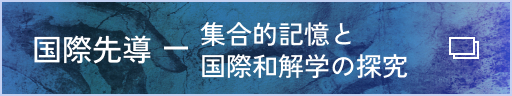最新プロジェクトはこちらをクリック▼
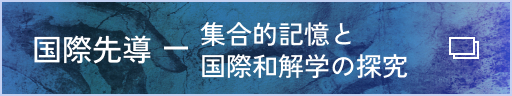
著書・論文(研究業績:著書・論文等)
2007年度
- 帝国日本の植民地法制―法域統合と帝国秩序』 名古屋大学出版会 (2008/2、単著)
- 帝国の起源と展開・変質・消滅についての法的実証分析によって、民族同士の共存の在り方を歴史の中に考察。「未発の可能性」としての地域主義と、それを圧倒していった帝国主義との間での相克、帝国解体後の戦後日本誕生のプロセスについて、問題提起。
2006年度
- 『南洋群島と帝国・国際秩序』 慈学社 (2007/2、単編著)
- ミクロネシア、パラオ共和国等の島嶼地域は、日米の戦略が交錯する空間であった。戦前は、沖縄県民を中心に朝鮮総督府の後援で移民が展開された。南洋引揚者の戦後日本への再統合過程、戦後琉球独立論の南洋再帰還運動との関係が明らかにされた。
- 『国境を越える歴史認識―日中対話の試み』 東京大学出版会 (2006/5、共著)
- 日中の若手研究者の国際的協力によって、微妙な歴史問題に大胆な解釈を提示したもの。靖国神社、戦争賠償、教科書、侵略の起源、傀儡政権が全体の主要テーマ。植民地時代の台湾史が日中の自国史にいかに組み込まれ、論争されているのかを論じた。
- 日中戦争の国際共同研究 2 日中戦争の軍事的展開』 慶應義塾大学出版会 (2006/4、共著)
- 廬溝橋の局地紛争が拡大し全面戦争となり国際的干渉が喚起された史実を、日中米台の研究者が自国の公式見解から自由に共同研究を推進。エズラ・ヴォーゲル先生の呼びかけによってハーバード大アジアセンターが主催、ハワイ・マウイ島で討論を交わす。
2005年度
- 岩波講座「帝国」日本の学知 第一巻 帝国編成の系譜』 岩波書店 (2006/2、共著)
- 国内法・国際法という二分法で理解不能な重層的秩序としての帝国の社会構造が全体テーマ。日露戦後、英国からの借金による韓国保護のもとで、アメリカ人の在韓治外法権廃止を推進する過程、在韓日本人の非難により保護が併合へと変質する過程を分担。
- 『故郷へ―帝国の解体と米軍が見た日本人・朝鮮人の引揚げ』 現代史料出版 (2005/9、単著)
- 敗戦後の日本帝国解体過程は、現代の北朝鮮問題と戦後日韓関係をひもとく原点である。金日成一家の家政婦として信頼された日本女性、華北と満州からの米軍船舶と日本船員による朝鮮人引揚、日本人の強制追放と脱北日本人難民に対する米軍撮影の写真と編者解説。
- 日露戦争の新視点』 成文社(日露戦争研究会編) (2005/5、共著)
2004年度
- 植民地帝国日本の法的展開』 信山社 (2004/7、共編著)
- 日本が中心となった東アジアの帝国秩序を、明治日本の条約改正との関連、国際関係の中の「法域」と領事館法制の機能、ドイツ帝国との比較、中国と満州での治外法権制度の展開、そして大東亜共栄圏を支えた国際法学会での議論などから明らかにした。
- 『植民地帝国日本の法的構造』 信山社 (2004/4、共編著)
- 朝鮮人や台湾人を包摂した日本帝国とはどのような国家であったのか、観念やイデオロギーに惑わされず、国家と社会の構造的性格に迫ったもの。国民を定義する国籍法、憲法、民事法と刑事法・裁判制度、参政権、徴兵制の植民地施行問題を論じた。
- 『記憶としてのパールハーバー』 ミネルヴァ書房 (2004、共著)
2003年度
- 「台湾のオーラルヒストリー「口述歴史組」の活動」 政策研究大学院大学『オーラルヒストリー』No.9 (2003/7、調査報告(単独))
2000年度
- 「日本帝国の統治原理『内地延長主義』と帝国法制の構造的展開」 中京大学社会科学研究所『社会科学研究』第21巻第1 ・2号 (2001/3、論文(単著))
1999年度
- 「戦場の盾にされた「慰安婦」たち」『世界』 岩波書店 (1999/11、論文(単著))
- 防衛庁に残された日本側兵士の体験記回顧録とアメリカ、台湾の資料を照合し軍隊中の慰安婦の位置を検討。最前線陣地に慰安所が設けられる際の意見の違い、敵の侵攻が迫る状況での慰安婦の後方避難について、「民間人」と軍の関係がより詳細に明らかとなった。
- 『近代日本文化論講座2 日本人の自己認識』 岩波書店 (1999/7、共著)
1998年度
- 『「慰安婦」問題調査報告』 アジア女性基金 (1999/3、共著)
1997年度
- 『甦る朝河貫一』 国際文献印刷 (1998/1、共著)
1996年度
- マーク・ピーティ著『植民地』(二十世紀の日本シリーズ第4巻) 読売新聞社 (1996/12、翻訳(単著))
- 明治国家の国民統合モデルと、欧米植民地モデルの折衷という視点から、日本の植民地統治五十年を、樺太・関東州・朝鮮・台湾・南洋群島について論じた本。本書は日本における植民地史研究にとって、スタンダードな教科書的存在と今もみなされている。
このページのトップへ