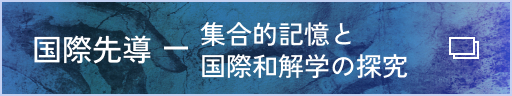ご挨拶

早稲田大学政治経済学術院・浅野豊美のホームページです(旧版修正中)。長い休眠期間を経て、早稲田大学で、2015年度からお世話になってきましすた。今まで、ほとんどご挨拶もできないままになっておりました方々には、誠に失礼を致しましたことお詫び申し上げます。
早稲田大学での授業を中心とする生活が、2015年から2017年の6月末まで続きました。その後は、新領域プロジェクト「和解学の創成」の合格が伝えられたことで、研究中心、しかし、実際はアドミニストレーション中心の生活となってきました。ようやく今、研究中心の生活が出発です。
近況ご報告
今の大きな焦点は、戦後直後に存在していた強力な感情(「理不尽」な戦争で失われた人命や、残され破壊された財産に付着していた感情)が集団的なものへと記憶と共に変化したであろう過程を、賠償問題が経済協力の問題へと変化する過程と交錯させながら論じることです。それによって今まで第二次大戦の賠償問題を実証的にたどり、その延長線上に日韓国交正常化を位置づけてきた研究を発展させていきたいと思っています。実証的研究の発展によって「記憶」というある意味ではつかみどころのない存在を、外交史を柱に、それと言説分析を組み合わせることで、しっかりと捉えながら、賠償問題が物理的な世界を復興させた一方、「心」や価値の問題が政治の主流から忘れ去られ、あるいは封印されてきた過程を明らかにしたいと思います。それは、より国際的で普遍的といえる価値にもかかわるものと思っています。
そんな思いを込めて新領域プロジェクト和解学創成の中の「和解三原則」を提唱しています。
実証的な研究の原点は、『帝国日本の植民地法制』(名古屋大学出版、2008年)であることはいうまでもありません。帝国の法秩序の上に存在していた「いのち」や「権利」を、条約と国内法の上に置き換えていく作業こそが、国交正常化であり、また、占領であったといえると思っています。
敗戦で失われた東アジアという地域を支える正義を、平和や民主主義という新しい価値を基盤としながら、いかに再生することができるのかを問い続けたいです。それこそが占領から国交正常化プロセスで問われ、しかし、激しい左右の価値の対立に直面して封印され、現在も「歴史認識問題」というアイコンの影に封印されている問題なのだと思っています。詳しくは、是非、新領域プロジェクト和解学創成のホームページをご覧ください。
今後とも、早稲田大学を拠点として、新しい次元での活動を続けてまいります。今までお世話になりました方々に感謝申し上げつつ、今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。(2018年9月20日)
- 2016年
- 浅野豊美「帝国日本の解体と戦後アジア」土田哲夫編『近現代東アジアと日本-交流・相克・共同体』中央大学出版部、2016年 181-207頁。
- 2016年
- オーストラリア国立大学が中心となって編集した以下の書籍の中の最初の章を担当して、初めて日韓併合の問題を英語で論じました。日韓の保護と併合が、今日の歴史問題の底流でくすぶり続けています。韓国人にも、日本人にも受け入れられる枠組みをめざしています。
‘Regionalism or Imperialism: Japan’s Options towards Protected Korea after the Russo-Japanese War, 1905-1910, Danton Leary and Pedro Iacobelli ed., ‘Transnational Japan as History: Empire, Migration, Social Movements, London: Palgrave MacMillan,2016. - 2016年
- 福島第一原発が立地している場所の一部は、かつて大陸からの引揚者が入植し、ブラジルに再移民していった場所でした。その後に原発は福島にやってきました。「福島のチベットと呼ばれた場所に原発を作ったのは福島の地方エリートたちでしたが、彼等は野口英世(千円札)と星一(SF作家新一の父)を通じて、GEを創設したエジソンや 植民政策学につながっており、巨大テクノロジーへの信仰を有していました。出稼ぎしなくてもいい場所、移民しなくても良い場所を求めていたのです。
「移住・引揚・国内定住地としての福島と原子力発電所-地元エリート・県人会移民ネットワークを中心に」根川幸男・井上章一編『越境と連動の日系移民教育史―複数文化体験の視座』ミネルバ書房、2016年。 - 2015年
- 昨年度、アメリカのワシントンにあるウィルソンセンターに滞在させていただいた際は、戦後70年談話はじめ歴史認識をめぐる各種の声明が飛び交いました。その流れの中でまとめた成果が以下です。
‘National Sentiments in Japan and Controversy over Historical Recognition: The Political Background of the Murayama Statement and its Development,’ Shihoko Goto , Zheng Wang and Tatsushi Arai ed., Contested Memories and Reconciliation Challenges: Japan and the Asia-Pacific on the 70th Anniversary of the End of World War II, Woodrow Wilsoncenter, 2015 - 2015年
- 今までの日韓国交正常化に関する研究を、分かりやすく集大成したのが以下です。
「民主化の代償-「国民感情」の衝突・封印・解除の軌跡」木宮正史編『日韓関係 1965-2015 Ⅰ 政治』東京大学出版会、 2015年6月、349-370頁。 - 2015年
- 1990年代が、自分が大学院生として、汗し涙した時代が歴史になった。そんな感情を込めながら、歴史認識問題の起源を探ったのが以下です。
「第1章 歴史と安全保障問題・連環の系譜―戦後五〇年村山談話と戦後七〇年安倍総理訪米」木宮正史編『シリーズ日本の安全保障(全八巻)第六巻 朝鮮半島と東アジア』岩波書店、2015年、15-44頁。 - 2014年
- 「帝国日本の形成と展開―第一次大戦から満洲事変まで」吉田裕・李成市他編(大津透・桜井英治・藤井讓治)『講座日本歴史 第一七巻・近現代三』岩波書店、2014年12月、35- 70頁(総328頁)
- 2013年
- (共著)『帝国日本と植民地大学』(酒井哲也・松田利彦編)ゆまに書房、2013年12月。「京城帝国大学からソウル大学へ-ランドグラント大学としてのミネソタ大学の関与と米韓関係から見た帝国的遺産」499-536頁。
- 2013年
- (共著)『未完の解放(미완의 해방)』李東俊(이동준)編、アジア研究所出版部、2013年8月。「帝国清算過程としての日韓交渉-サンフランシスコ講和条約と日米関係との関連から」を担当。
- 2013年
- (単編著)『戦後日本の賠償問題と東アジア地域再編―請求権と歴史認識問題の起源―』(共同執筆:李東俊・樋口敏広)慈学社、2013年2月。
- 2013年
- (共著)『大韓帝国の保護と併合』森山茂徳・原田環編、東京大学出版会、2013年2月。「国際関係の中の『保護』と『併合』――門戸開放原則と日韓の地域的結合をめぐって」227-253頁。
- 2012年
- "Historical perceptions of Taiwan's Japan era." Toward a History Beyond Borders: Contentious Issues in Sino-Japanese Relations: Harvard East Asian Monographs ed. By Daqing Yang, Jie Liu, Hiroshi Mitani, Andrew Gordon, Harvard University Asia Center, April 2012, pp. 229-339.
- 2012年
- 2012年から2011年にかけては、日韓国交正常化に関する実績をたくさん発表いたしました。それを前進させなければと考えるこの頃です。
「史料が語る日本外交6 日韓請求権問題の歴史的起源」『外交』12号、外務省、2012年3月、84-87頁。 - 2011年
- (共編)『歴史としての日韓国交正常化-東アジア冷戦編』(木宮正史・李鍾元と共編)法政大学出版局、2011年2月。
(共編著)『歴史としての日韓国交正常化-脱植民地化編』(木宮正史・李鍾元と共編)法政大学出版局、2011年2月。(「サンフランシスコ講和条約と帝国清算過程としての日韓交渉」を執筆) - 2011年
- 「サンフランシスコ講和条約と帝国清算過程としての日韓交渉」財団法人日韓文化交流基金『訪韓学術研究者論文集』第11巻、141-176頁
- 2011年
- 「戦後日本の国民再統合と『贖罪』をめぐる対外文化政策」
中京大学『国際教養学部論叢』第3巻第2号、29-58頁。 - 2011年
- 「東アジア地域主義と日韓の歴史認識パラダイム」(日韓対訳)
東京大学大学院情報学環現代韓国研究センター『東アジア共同体と日韓の知的交流』、1-52頁 - 2011年3月
- 『1920年代の日本と国際関係-混沌を越えて「新しい秩序」へ』(杉田光行編)
春風社、 第8章「日ソ関係をめぐる後藤新平と幣原喜重郎-体制共存・変容をめぐる政治経済史の視点から」P279-322頁 - 2011年2月
- 『岩波講座 東アジア近現代通史第七巻 アジア諸戦争の時代1945-1960年』(木畑洋一編)岩波書店
敗戦・引揚と残留・賠償‐帝国解体と地域的再編」71-96頁 - 2010年
- 千倉書房より「ポーレー・ミッション―賠償問題と帝国の地域的再編」小林道彦・中西寛編『歴史の桎梏を越えて-20世紀日中関係への新視点』が発行されました。
→この本は大平正芳賞を受賞し、編者の小林先生、中西先生が、授賞式に臨まれました。 - 2009年10月17日
- 日本思想史学会の公開シンポジウム「日本思想史からみた憲法―歴史・アジア・日本国憲法」(13:30~17:00)にて、「折りたたまれた帝国としての戦後日本と東アジア地域形成 」を報告しました。
大会参加記にてご紹介いただき、ありがとうございました。 - 2009年
- 龍渓書舎より浅野豊美編『大東亜法秩序・日本帝国法制関係資料 第3期 満洲国関係・蒙彊政府関係資料 第21巻-第36巻』を出版しました。
- 2009年6月20日
- ミネルヴァ書房より『伊藤博文と韓国統治』(伊藤之雄・李盛煥編)が出版されました。これは2008年秋に京都で行われたシンポジウムの成果の一部です。
→目次と序論(私の分担、第7章「日本の最終的条約改正と韓国版条約改正」の紹介です) - 2009年6月12日
- 第25回大平正芳記念賞を受賞しました。
東京丸の内の日本工業倶楽部にて、約400人の招待客を前に授賞式が行われました。 - 2009年3月25日
- 第38回吉田茂賞を受賞いたしました。
- 2008年
- 名古屋大学出版会より、単著『帝国日本の植民地法制―法域統合と帝国秩序』を出版しました。
上記を提出し、東京大学総合文化研究科国際社会学専攻課程より、論文博士の学位(学術博士)を2009年2月に取得しました。